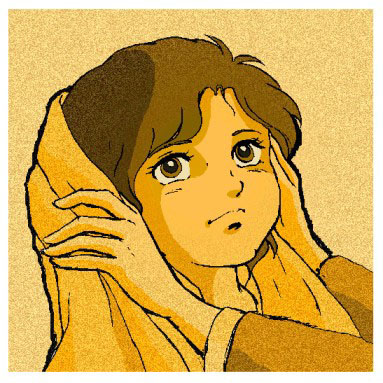
| |前ページへ|ファンフィク部門トップへ| |
| 快晴の陽射しに照らされた飛行場は、昨夜の雨で濡れた芝生を日の光にきらめかせながら、新鋭機を誘導路に抱いて実験の開始を待ち受けている。 肩に羽織ってきたショールを管制室に置いてきてしまったが、外はもう十分に暖かかった。 「ママ、こっち!」 子供に手を引かれながら案内の係員が示してくれた位置に子供と並んで立つ。 |
| 南部博士と話し込んでいた父親は、こちらをちらりと見やってからテスト機に歩みより、整備員の一人から受け 取った整備状況の記録を点検し、確認のサインをしている。 さらに機体外部のチェック・リストの点検が終了するとようやく彼はコックピットに落ち着いた。 整備員はエンジン始動を意味する手信号を確認しながらも機体全体の様子を見守っている。エンジンが回転数を上げて推力を発生しはじめると、管制塔からの指示を受けたパイロットから『車輪止め外せ』の合図が送られてくる。 翼の下に入った整備員により車輪止めが外されると、パイロットからはブレーキリリースの合図があり、機体全体を注視しているベテランの整備員からは、滑走路の方へ機体の向きを変えるよう手信号の合図が送られてきた。 テスト機を見送るために一列に並んだ整備員達が姿勢を正したのにならって、子供も小さな身体をまっすぐにし緊張した表情になっている。小さな手が白い手から。挙手の敬礼に見送られて、テスト機の地上滑走が開始された。 |
| いきなり子供が走り出した。大人たちの声が上がる。意外とスピードがありすぐには追いつくことができない。 テスト機は力強く滑走路を蹴って大空に駆け上っていく。 と、昨夜の雨で濡れた草に足をとられて子供が転んだ。が、跳ね起きると、みるみる小さくなってゆく父の機を追って再び走り出す。 そこで大人たちとの距離が縮まった。ようやくもっとも若い職員がすぐ後ろまで追い着き手を伸ばしたところで再び子供が転んだ。 勢い余って彼はすぐそばを走り抜けてしまい、数メートル先でUターンすると戻ってきた。 転んだときに痛めたのか、子供は土のついたふっくらした頬にいく筋も涙をつたわせて父の愛機が吸い込まれていった南の空を見つめている。その視線の強さにしばしたじろいだ彼は役目を思い出した。 「ぼうや、大丈夫かい?」 声をかけながら抱き起こそうとすると、子供はよろめきながらも自分から立ち上がった。泥だらけの小さなひざに血が滲んでいる。 「痛いかい?」 職員が訊ねたのに子供は返事をせず、くちびるを噛み締めるようにして首を振った。残りの職員たちが、まわりに集まってきた。ひとりが気づいて服のよごれを払ってやりかけたところに澄んだ呼び声が近づいてきて、子供は弾かれたようにそちらへ走っていく。すんなりと伸びた足が力強く地面を蹴った。 管制塔の一隅に備わっている職員用の宿泊エリアに案内され泥だらけの顔や手足を洗ってやり、ひざの様子をみながら着替えをさせた。濡れた髪をていねいに拭いてやっていると 「パパは帰ってくるの?」 不意に小さく、だが、はっきりと訊ねてきた。 「ええ、お仕事がすめばね。」 「いつもそうでしょう?」 子供は答えず、タオルの陰から大きな青い眼でじっとこちらを見つめている。何やら胸をかすめるものを覚えたが 「パパのお帰りまで、ママとお留守番をしましょうね。」 強いて声を明るませ微笑みかけると 「うん。」 子供はうなずき母の胸に飛びついてきた。 |
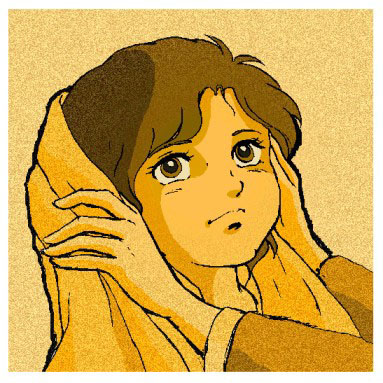
| さすがに疲れて寝入ってしまった小さな身体を抱き寄せふわりとショールを掛けてやりながら、車に揺られていた。 (なぜ、この子は走りだしたのだろう?) 往路とは違う職員がハンドルを握っているので幾度か道を尋ねられ、そのたびに思考は遮られた。 送ってきてくれた職員には荷物を頼み、ショールごと子供を抱き上げた。4才とはいえ眠るとずっしりと重い。 「ん…」 母親だけが知っている、決して起こさないやり方で子供を抱いて家の中へ入った。 |
| 車のエンジン音が遠ざかっていくのを聞きながら、子供を寝かせたソファの近くにそっと腰を降ろした。 ふさふさした濃い色の髪はすっかり乾き、かわいい寝顔の中で長い睫毛が頬に濃く影を落としている。この睫毛とふっくらした頬の線は優しいが、年毎に整ってくる顔立ちの中で濃い眉と引き結んだ口もとは、まぎれもない男の子のものだ。 先月に引き込んだ風邪が抜け切らず、なんとなくこの頃、疲れやすくなってきている自分に比べて子供が丈夫で利発なことが何よりもうれしかった。すべての母親がそうであるように自分の子供は世界中で一番愛らしく賢いと信じこの子の上には良い事ばかりが起こるよういつも祈っていた。 (なぜ、この子は走りだしたのだろう?) あれほど言い聞かせたことや言いつけは良く守っていたのになぜ今日になって、それも父親の離陸の瞬間になって、なぜ? 「ん…」 子供がショールを跳ねのけた。そっと掛けなおしてやっていると今朝からのことがよみがえってきた。 |
| 雨上がりの朝、仕度をして迎えの車を待つために子供をつれて外に出ると空気は思いがけず冷んやりとしている。 はしゃぐ子供がぐいぐいと引っ張るのにつないだ手をとられて、もう一方の腕に掛けたままになっているショールを、細い肩先をふるわせた妻を気遣い、夫が羽織らせてくれた。 子供と夫の世話に夢中になるあまり、何事も後回しになる自分のことを夫はいたわり、支えてくれる。 このショールも、ついこの前に贈ってくれたものだ。 いつの間に憶えてくれたのか、好きな色でもあるのがうれしい。 ショールも含め、万が一と思って用意したものが役に立ったり、子供が父の機の後を追ったり、まさかと思っていたことがことごとく起こる、この一日にふと胸が騒いだ。 |
| 「ママ、おやつ」 いつ目覚めたのか、窓際の椅子に移ってもの思いに沈んでいた母のひざを小さな手が揺すり、眼が合うとそのままひざへよじ登ってきた。両手を廻してくる小さなあたたかい身体を抱きしめ、ふっくらした頬にほおずりしながら次々と胸の中にわき起こってくるものをなんとか鎮めようとした。 |
| |前ページへ|ファンフィク部門トップへ| |